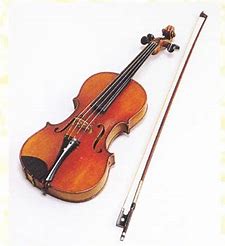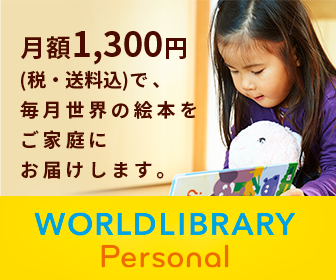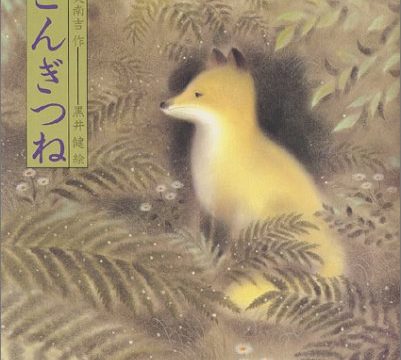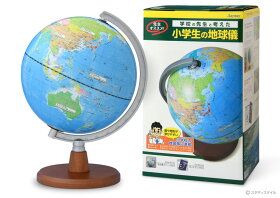女の子の習い事で、メジャーな習い事のひとつに「ピアノ」があると思います。
次に聞くのが「ヴァイオリン」ですが、圧倒的に「ピアノ」が多いのではないでしょうか。
なんとなく、「ヴァイオリン」に、ハードルの高さを感じている人が多いと思います。
実は、私もそうでした。
私の本業は、音楽家なんですが、それでも、ヴァイオリンの人達は、少し違う世界の人、よりマニアックな人達という気持ちが少なからずありました。
今、二人の子供達にヴァイオリンを習わせていますが、その中で気づいた、ヴァイオリンを習うことのお勧めポイント、習う上できをつけたいこと、コツなどなどを徹底解析していきたいと思います!
Contents
なんでヴァイオリンはハードルが高いと思うのか?
- 楽器が高い?
- ヴァイオリンの世界は閉鎖的?
- 音楽を専門にする人以外受け入れられにくい?
- 先生が怖そう?
- 弾くのが難しい?
こんなイメージでしょうか?
実は、これら全てが本当にその通りで、全てがそんなことはない、と言えるんです。
ヴァイオリンの楽器は高いのか?
これは一番ある懸念材料だと思います。
でも、本当に高いんでしょうか?
確かに、日本音楽コンクールで入賞したいとか、国際コンクールに出たいとか、プロのオーケストラに入団したいとか、音楽家としてやっていくようなレベルの人なら、その人がもっている楽器は、持ちたいと望む楽器は、非常に高いと思います。
それこそ、天井知らずに。
でも、初心者にはどうでしょう?
始めるのが3歳、4歳なら?
ヴァイオリンには分数サイズがあるのをご存じでしょうか。
チェロにもあります。
(ちなみに、ビオラにはありません。まずヴァイオリンで基礎を学び、のちにビオラへと転向するという経緯をたどります。)
ヴァイオリンは早いと2歳から始める人もいますが、2,3歳だと1/16の楽器になります。
(1/32も存在するようですが、非常にレアで、楽器店ではほとんど見かけません。しかも1/16さえ持てないくらい小さい子が、お稽古を始められるかというのも疑問です。)
分数サイズと適した身長、価格表
| ヴァイオリンサイズ | 適した身長 | 価格(YAMAHA公式HPより) |
| 1/16 | 105cm以下 | V5SC 希望小売価格: 57,000 円(税抜) |
| 1/10 | 105cm-110cm | V5SC 希望小売価格: 57,000 円(税抜) |
| 1/8 | 110cm-115cm | V5SC 希望小売価格: 57,000 円(税抜) V7SG 希望小売価格: 82,000 円(税抜) |
| 1/4 | 115cm-125cm | V5SC 希望小売価格: 57,000 円(税抜) V7SG 希望小売価格: 82,000 円(税抜) |
| 1/2 | 125cm-130cm | V5SC 希望小売価格: 57,000 円(税抜) V7SG 希望小売価格: 82,000 円(税抜) |
| 3/4 | 130cm-145cm | V5SC 希望小売価格: 57,000 円(税抜) V7SG 希望小売価格: 82,000 円(税抜) |
| 4/4 | 145cm以上 | V7SG 希望小売価格: 82,000 円(税抜) V10G 希望小売価格: 119,000 円(税抜) |
実際サイズを決めるのは、腕の長さによるところが大きいので、一概に身長だけではありませんが、おおよその目安です。
つまり5歳くらいまでの間に始めるとして、1/16、あるいは1/10を購入するわけです。初期投資という意味で、最初に持つであろうヴァイオリンとピアノの価格比較をしてみます。
ピアノと1/16、1/10のヴァイオリンの価格比較
日本で最大手の楽器メーカーであるYAMAHAで、これらの分数サイズのヴァイオリンの価格とアップライト、またグランドピアノの価格を比較してみたいと思います。
| 楽器 | 価格帯 |
| 1/16のヴァイオリン | V5SC 希望小売価格: 57,000 円(税抜) |
| 1/10のヴァイオリン | V5SC 希望小売価格: 57,000 円(税抜) |
| アップライトピアノ | YU11 希望小売価格: 660,000 円(税抜) 商品中最低価格 SU7 希望小売価格: 2,400,000円(税抜) 商品中最高価格 その他この間に多数のタイプがあります。 |
| グランドピアノ | GB1K 希望小売価格: 1,150,000 円(税抜) 商品中最低価格 C7X 希望小売価格: 3,500,000 円(税抜) 商品中最高価格 その他この間に多数のタイプがあります。 |
なお、ピアノにはこのほか、電子ピアノがありますが、基本的に、ピアノのタッチにそっくり!と銘打っていても、ファンクションが全く違いますので、ピアノと電子ピアノは別物です。電子ピアノは電子ピアノで非常に有用なものですが、ピアノのお稽古を始める、ピアノを弾くという意味で代わりになりうるものではありません。
なお、ヴァイオリンは2万円くらいで、本体、弓、楽器ケースが全て揃う中国製のものや、ヤマハ以外にもスズキのヴァイオリンなど安価なものはあります。これはピアノも同様です。あくまでも、一つのサンプルとしてYAMAHAで比較しましたので、この価格が全てではないとご承知おきください。
どこで買う?
ヴァイオリンはどこで買えば良いでしょう?
安価という意味では、ネットが一番だと思います。
ですが、もし、お子様のお稽古として細くても、長く続けさせたいと思われるなら、
できたら発表会も出してあげたい、数年は続けさせようとお思いならば、
楽器店でお求めになることをお勧めします。
弦楽器の楽器店というのは、
楽器を打っている場所でもあり、また、作っている職人さんがいる場所でもあります。
もちろん、スズキやYAMAHAもその一つです。
その楽器店の中でも、一番お勧めなのは、
大手の会社がおこしているのではない、個人の職人さんを抱えている、楽器店です。
なぜかというと、大手の会社ですと、基本的に自社製品が中心になりますが、
ヴァイオリンは今メーカーで量産されているものより、
オールドの楽器をメンテナンスし直したものの方が圧倒的に良い音が出ます。
そして、そういう個人の楽器店には、スズキもヤマハも取り扱いがありますし、
もし、なくても、頼めば、ネットなりなんなりでそこで取り寄せてもらえますので、
選択肢が広がります。
最初に手に入れる分数サイズは、そこまでこだわらないとお思いかもしれませんが、
1/10、1/8にはあっという間になりますし、
この時の楽器の選定力やメンテナンス力の差は、驚くほどの差となります。
ヴァイオリンはメンテナンス次第で、買った価格よりも高く売れることがあります。
最初はどんどんサイズが大きくなり、楽器を買ったり売ったりするので、
リセールも考えて、良い職人さんのいる楽器店で買いたいものです。
子供の1/10のヴァイオリンを、二つの楽器屋さんに持っていき、メンテナンスしてもらったことがありますが、価格が違うヴァイオリンにすげ変わったのかではないかと驚くほどの差が出たことがあります。弦楽器にはメンテナンスは必須。弓の毛替えも、同じ弓でも取り換えたのかと思うほどの差がでますので、職人さん、楽器屋さんは大切です。
楽器屋さんの見つけ方
一番良いのは、紹介です。
誰かから評判を聞いて、突然行っても大丈夫ですが、一番は紹介が安心です。
まったくツテがなければ、習う先生が行っている楽器屋さんや、先生がお弟子さんに紹介している楽器屋さんを紹介してもらいましょう。
先生によっては、最初の分数サイズのうちは、先生が所持している楽器をお弟子さんに貸してくれる先生もいるようです。これは先生のポリシーによりますので、貸してくれますか?とは聞かない方が賢明です。貸してくれるタイプの先生は、聞かなくても、お貸ししますと申し出てくれるはずですので。
どの程度の物を買う?
これはもう、予算による、につきますが、
最初の分数サイズの楽器としては、スズキでも、YAMAHAでも中国製でも、
どれでも大丈夫だと思います。
とにかく良い職人さんを見つけて、良い調整をしてもらうことが大切です。
例えばフルサイズでも、10万程度の中国製でも、それなりに良いですし、30万くらいまで予算を広げられるなら、チェコのオールドなど、ヨーロッパの古い楽器にまで手が届きます。プロでやっていくのでないなら、これでもう十分です。
ちなみにリセールですが、ピアノは打楽器で消耗品と考えられるため、納入した時点で一音も弾いていなくても、買取価格は元の値段の3割くらいが相場ですが(実体験あり)、ヴァイオリンはメンテナンスさえしっかりして、楽器の状態を良くしておけば、元の価格通りか、状態によっては、より高く売ることも可能です。
どんな先生が良い?
音楽の先生は、一対一のレッスンなので、相性がとても大切です。
どんなに高名な先生でも、相性が合わないと成長につながらないこともあります。
より相性の良い先生を見つけるためには、どんなことに注意したら良いのでしょうか。
私たちにも、こんな先生が良いな、と思う理想のタイプがいるように、実は指導者の側にも、理想とするターゲットの生徒像があります。
1)毎日一生懸命練習して、親子二人三脚で取り組むような、本気の生徒を教えたい先生
2)そこまでは行かなくても、家庭での練習は親が付き合ってみてあげて、レッスンにも同伴してくるような、習い事としてきちんと努力する生徒を教えたい先生
3)基本的に親の介入がなく、子供の自主性に任せていて、毎日練習するわけではない生徒でもウエルカムな先生
4)どのパターンの生徒でも、臨機応変にみんなウエルカムという先生
この、指導者が望むターゲットから、どのパターンだとしても、はずれていると、お互いに非常にやりにくくなってしまいます。
まず、お子様に
1)基本的には、毎日ある一定の時間練習するように指導するのか
2)子供が嫌がる時には、嫌がっているのに練習を強いるようなことはしない方針なのか
3)レッスンで一緒に練習してくれるような先生が良いのか
などなど、ご自分の方針をはっきりさせてから、先生をえらぶと良いと思います。
どこで先生を見つけるか?
一番お勧めなのは、「子供を教えるプロ」の先生を見つけることです。
「ある程度の技術を会得した後の高校生や大学生に、コンクールで入賞するような音楽性を教えるのに長けている先生」と「初めて楽器を持つ子に、基礎を教えるのに長けている先生」とは違います。
続けていくうちに、本格的に音楽の高校や、音楽大学に進学したいとなれば、その時に、その時師事している先生から、その先の先生を紹介してもらえば良いわけですから、まずは「子供を教えるプロ」に師事することをお勧めします。
「〇〇大学付属 子供のための音楽教室」には「子供を教えるプロ」がたくさんいます。しかも、指導者は基本的には、その〇〇大学の出身者なので、そういう意味で安心感もあります。
イメージでは、プロになる人以外難しそうと思われるかもしれませんが、実はそうでもなありません。それぞれの音楽教室の本部校は確かにその傾向があるかもしれませんが、支部は、あくまでも趣味でやっているという生徒さんがたくさんいます。
また、そこまでは抵抗があるという方は、音楽大学の同窓会に問い合わせてみてください。だいたい、同窓会にはその大学の卒業生がレッスン講師の登録をしていることが多く、希望の条件などを示すと紹介してもらえると思います。
地元で長年にわたりたくさんの生徒を集めて指導している先生に心当たりがあれば、それも、もちろんすごく良いと思います。
毎日の練習を習慣化する
ヴァイオリンを演奏する楽しさを感じられるのは、実は結構あとです。
これはどの楽器でも、全ての楽器に当てはまることです。
ヴァイオリンですと、まずどこを押さえると、どの音が鳴るのか知らなくてはなりません。弓も正しく持てなくてはならないし、弦をこするのも、ただこすれば良いわけではなく、ルールがあります。
そして、誰もが苦労するのに、楽譜を読むということがあります。
まずは楽譜の音が読めるようにならないと弾けませんし、音符の種類を覚えて、リズムがとれるようにならないと、演奏できません。
これは、赤ちゃんが、ハイハイができるようになり、だんだん立とうとして、つかまり歩きから、徐々に歩けるようになり、安定して歩けるようになり、走れるようになり、さらには様々な運動ができるようになる、というステップによく似ています。
まずは、少なくても自分でしっかり歩けるようになる、くらいまでの段階にならないと、演奏の楽しさは味わうことはできません。
楽器演奏の習得は歩行の習得、語学の習得と非常に似ていて、
毎日少しずつでも良いから、積み重ねていくことが大切です。
その日はできなくても、日々同じことを繰り返すことで、体が自然と覚えていき
一週間後、一か月後にはそれが出来るようになる。
これが楽器演奏において、とても大切なことになります。
日々の練習のサポートのための秘策
これは、お母さまご自身が全くヴァイオリンの経験がないけれども、お子さんのヴァイオリンのお稽古をとても真剣な習い事として考えているお母さまにだけ、お勧めの方法です。
まず、お子さんが始める前にご自身が半年くらい、同じ先生に習ってみてください。この時のヴァイオリンはレンタルという手もあります。
最初の段階で、お子さんの練習の時に、弓を持って一緒に弾いてあげられることが、大きなサポートになりますし、音程を作る左手の取り方も、ほんの少しでも知っているのと、そうでないのとでは、本当に違います。
半年、というのは、子供の成長は速いので、どうせ大人は追い抜かれますし、
自分が弾くわけではないので、少しだけ経験しているだけでも、レッスンで先生が何を注意しているのか、ポイントをつかむことができます。
ここからは、一般的なポイントですが
お子さんおひとりでは、レッスンでたった一度先生が言ったことは一週間記憶していられません。
また、練習中、先生のアドバイスを思い出して、注意深く練習することも不可能です。
少なくとも、最初の数年は、毎日は難しくても、お子さんの練習の間そばにいて、レッスンでのポイントや注意を伝えてあげること、実際お子さんが演奏している内容への感想を言ってあげることが、お子さんの成長には不可欠だと思います。
一日の練習時間の目安ですが、最初の数か月以外は、レッスンと同じくらいの時間するのが適当と言われます。レッスンを受ける意味での体力もつきますし、レッスンで弾く曲を練習するわけですから、その分量としても適当と考えられています。
楽譜は自分で読めないとダメ!?
スズキメソードを聞いたことがありますか?
ここは、最初の段階では読譜はせず、先生が演奏して、それをまねることからスタートするもので、本格的にプロの道を志す時に、楽譜を読む力が不足していて、弊害を生むともいわれていますが、いきなり、読譜をさせて、それでストレスをためてしまうより、まずは親が横で歌ったり、一緒に楽譜を読んで教えてあげて、どんどん楽器を弾くことが大切だと思います。
公文と同じで、何度も何度も繰り返し繰り返しすることで、頭の柔らかい子供は知らず知らずのうちに楽譜を覚えていきます。
1年か2年経った時期を見て、こんどは何となくわかっている音や音符を、もう一度、理論的にきちんと確認したら良いのです。
お稽古には親が同伴するか?
これは先でも述べましたが、毎日の練習で、少しでもアドバイスできるように、なるべく同伴してあげましょう。
何を言われたか忘れそうな時はメモをとっても大丈夫です。
ただ、録音するのは、抵抗のある先生が多いと思うので、控えた方が無難です。
市民オケや大学のオケなどもあり、決してプロにならなくても生涯において楽しめるのがヴァイオリンです。ご自分のお子様のレッスンとして求めるニーズはをきちんと把握して、環境作りをして、楽しい音楽生活が送れるようにと願っています!
しぇんこ
7歳と3歳の姉妹を持つアラフォー&ワーキングママです。
女の子育児をこよなく愛し、育児に仕事に家事にと奮闘中。
女の子育児ならではの悩み、4歳差ならではの悩みに向かい合い、研究の日々。
長女誕生以来、自分なりにこだわって調べてきたことを、育児に奮闘中のママへお届けしたいと思っています。
詳しい自己紹介、ブログを始めるきっかけは最初の投稿に書きました。
よろしければ、お読みくださいませ!
しぇんこ